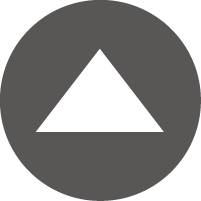- アジア・中東
- 北米・中南米
- 欧州・アフリカ・大洋州

民法
土地法
土地使用料法
財産権登記法
不動産担保法
土地法(Law on Land、2002 年制定、2003 年改訂)では土地に関する権利について、「所有」「占有」「利用」の三つの形態を認めている。
「モンゴルの全ての土地は国家のもの」というのがモンゴル憲法の一般的規定であるが、国家は土地を私的所有のためにモンゴル国民に配分できることが認められている。
一方、外国投資家/外国投資企業に与えられるのは利用権のみ。
国民は自ら所有する土地の区画を外国市民に譲渡することは禁止されている。土地の占有権は、利用目的に応じ国家との間で締結される土地占有契約の特定の条件に従って法的管理を有する占有者の権利であり、モンゴル国民と国内資本企業/組織にのみ与えられる。
土地利用権は、土地所有者(国家またはモンゴル国民)または土地占有権保持者との間の契約によって、土地の有益な特性を利用する権利である。
また、土地法では、外国投資に関わるモンゴル企業が特別の条件に従って土地を利用することを認めている。土地使用料法で土地の使用料が定められている。
鑑定評価業務の行うために、モンゴル国法務所や財務省より許可を受ける必要がある。
「財産鑑定法」には国際的評価基準や国内評価項目などによることが記載されているが、一般的に各社の取引事例を参考にしながら評価する。
1990年代のモンゴルにおける国有財産の民営化と民間部門の形成以来、不動産仲介業者は統合的な監督を受けずに運営されてきたためFATF(金融活動作業部会)によってマネーロンダリングとテロ資金供与の観点から「高リスク」とみなされ、重点監視対象国のリストにモンゴルが含まれるきっかけとなった。したがって、モンゴルはこの分野における政策、戦略、規制を改善する必要があり、これに応じて、FRC(モンゴル金融監督委員会)の法的地位に関する法律およびライセンス法が改正され(2020年1月17日)、FRCが不動産仲介業者の活動を規制および監督する権限が与えられた。
〔不動産関連法・制度の現状、土地・不動産の所有権〕
JICA「モンゴルビジネス環境ガイド」(2022年11月)
〔土地・不動産の登記〕
世界銀行 Doing Business「Data > Economy Snapshots >Mongolia > Regisering Property」
〔免許制度〕
World Bank「MODULE MONGOLIA HOUSING FINANCE TECHNICAL NOTE JUNE 2012」
FRC(モンゴル金融監督委員会)
土地使用権の譲渡について、土地所有法第38条に提出すべき必要書類を規定している。各種書類(土地所有証明書、不動産登記謄本、非担保証明書、税金支払領収書など)を確認した上、譲渡を受ける側または渡す側のどちらも国家登記局に譲渡申請書を提出する。
消費者権益保護法、民法、不動産法、担保法、競争法により規定されている。
都市開発・都市機能強化では、UB(ウランバートル)市への人口一極集中による交通渋滞や大気汚染の解消、逼迫する教育環境の改善等が課題となっている。これら課題の解決のためモンゴル政府は新空港周辺等における新都市開発計画を掲げ、多様なステークホルダー間の意見のとりまとめや実現性のある開発計画の策定に向け取り組みを開始している。
また、地方部から UB 市への人口流入が進む中、UB 市近郊部ではインフラが未整備であるゲル地区が無秩序に広がり、環境への悪影響が顕在化している。このため、UB 市はアパートへの居住を促進させるとともに、ゲル地区に居住を希望する住民に対するインフラ整備を実施している。
住宅金融の担い手は民間(銀行)であり、住宅購入時に住宅ローンを利用する人の割合は約60%である。住宅ローンの金利は一般的に固定金利である。住宅ローン利用時の貸出条件は、人的要件・建物要件があり、担保価値の評価は、銀行指定の鑑定員が行う。
2013年6月に、政府は、中所得者向けに住宅取得支援策として商業銀行を通じた低金利融資を提供することを発表した。この支援策は、中央銀行が商業銀行に対して年率4%で資金を融資し、商業銀行がその資金を一定の条件を満たした住宅取得者に対して年率7~9%の20年物固定ローンを貸し出すものである(現在は8%で貸し出されている)。支援策の適用条件の主なものは①正規雇用者であり安定した収入があること、②返済が月収の45%を超えないこと、③10~30%の頭金を用意すること、④住宅面積が80㎡を超えないこと、である。同支援策は、既存の住宅ローンの借り換えも対象としている。
2015年12月10日に、モンゴル銀行協会は低金利(8%)住宅ローンの新規融資を無期限停止すると発表した。
〔不動産行政の方向性〕
国際協力機構(JICA)「国別分析ペーパー」(2023年1月)
〔不動産金融〕
公益財団法人国際通貨研究所ニュースレターNo.17(2014年3月26日)「モンゴル銀行セクターの現状」
不動産に関する税は発生しない。
固定資産税は政府登記所への登記額の0.6%~2%である。
不動産譲渡所得(譲渡益) 10%
不動産譲渡所得 2%
但し個人の住宅購入及び建設費用の一部(30 百万 MNT までの所得:1 回のみ)課税対象外
日本とは未締結
〔不動産保有に関する税制〕
PwCコンサルティング調べ(2023年)
〔その他税制(租税条約等)〕
JICA「モンゴルビジネス環境ガイド」(2022年11月)
土地の保有権(占有権)とは、モンゴル国籍を有する自然人またはモンゴル法人が法律による要件で一定期間に土地を支配する権利をいう(土地法 3 条 1 項 3 号)。土地保有権には、所有権とほとんど類似する財産的支配関係が認められている。土地利用権は、外国人及び外国法人が土地を法律どおりに利用する権利である(土地法 3 条 1 項 8 号)
民法の権利義務の主体は、自然人、法人、法人資格なき機関である(7 条 1 項)。自然人には、モンゴル国民、外国人、無国籍者を含む(7 条 2 項)。つまり、モンゴルにおいて、外国人は、民事法上有する権利義務はモンゴル人と異ならない。唯一の違いは、前述の土地法による土地に関する財産権に関するもののみである。これは、モンゴル国憲法において、土地を所有できるのはモンゴル国民としていることに基づく。なお、モンゴルでは土地とその上に建てられた建物の登記が別々となっているため、建物は土地と別個独立した不動産として扱われている。建物を所有する主体に対しては、前述の憲法の制約は及ばず、外国人であっても特に制限がない。
「外国投資家」とは、モンゴル国において投資を行う、外国法人及び個人(モンゴル国に永住しない外国人及び無国籍者、外国に永住するモンゴル国民)である。
「外資系企業」とは、モンゴル国法令によって設立され、法人が発行した株式の総数の最低 25%を外国の投資家が所有し、外国の各投資家の投資金額は最低 10 万米ドル又は、それに相当するトゥグルグである事業体である。
投資法は、旧投資法(1993 年制定現行投資法の制定により失効。)と異なり、広く民間及び外国人投資家の投資を認めている。民間投資家の場合、モンゴル国法令で禁止された以外の業界、生産、サービスに対して投資を行うことができる。すなわち、民間投資家に対して投資法の適用範囲が比較的に幅広い。
外国及び国内の投資家は、会社法、法人国家登記法及びその他の関連法令により、国家登記に登記されたときから、モンゴル国において事業を行うことができる。
外資企業を含むモンゴルにおける企業が外国人を雇用するに際してはクオーター制度というものがあり、毎年閣議において、分野毎の外国人雇用枠を決定している。
建設業では、資本金が5億100万トグログ(約2,000万円)、従業員が50人未満の場合、20%までしか外国人を雇用できない。こうした割合は,分野毎,資本金額,総従業員数により異なるため注意が必要である。
2010年4月より、渡航目的に関わらず、モンゴル国を30日までの短期訪問する日本国民に対して査証を免除している。30日を超える滞在の場合、招聘機関・招聘者は、モンゴル国の外国人・国籍問題担当行政機関に長期滞在の申請を行い、適切な査証許可を取得する。当該機関の許可に基づき、駐日モンゴル国大使館領事部は、適切な種類の査証を発給する。書類がそろっていれば 3営業日でビザを発給する。
モンゴル国内で就労する場合、公務主管庁及びその有権機関の許可、外国投資企業の管理職として勤める場合は経済開発省外国投資調整登録局(旧外国投資貿易局FIFTA)から付与された証明書、労働保証サービス所から発行された就労許可書、滞在地域の知事による証明書、受入機関の願書等が必要となる。
2013年11月「投資法」第7条にて、雇用義務は記載ないものの、従業員の知識、経験、資格、技能を向上させることが投資家の義務として記載されている。
〔外資に関する優遇措置もしくは規制、外資参入の許認可制度〕
法務省「現地におけるビジネス関連法令の概要および整備の状況について」
〔外資参入の許認可制度〕
在モンゴル日本国大使館「最近のモンゴル経済」(2012年9月)(p.17,18)
日本貿易振興機構(JETRO)「モンゴル国投資法、モンゴル国投資法施行細則、モンゴル国投資契約締結規則」(2015年3月)
〔就労ビザ、長期滞在について〕
駐日モンゴル国大使館「ビザ」
現在は該当なし
現在は該当なし
調査実施時期:2021年9月
データベースはないが、計画(Land Management and Fiscal Cadastre project:LMFC)は立てられ、実行中である。
現時点で登記情報を確認するには、法務省にて登記簿謄本を閲覧するしかない(ただし関係者のみ)。
〔主要都市等におけるマーケット情報〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 投資コスト比較」
〔取引履歴・物件情報などのデータベース化〕
International Society for Photogrammetry and Remote Sensing「GIS BASED LAND INFORMATION SYSTEM FOR MANDAL SOUM, SELENGE AIMAG OF MONGOLIA」
スルガモンゴル 等
※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。